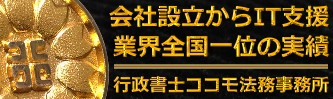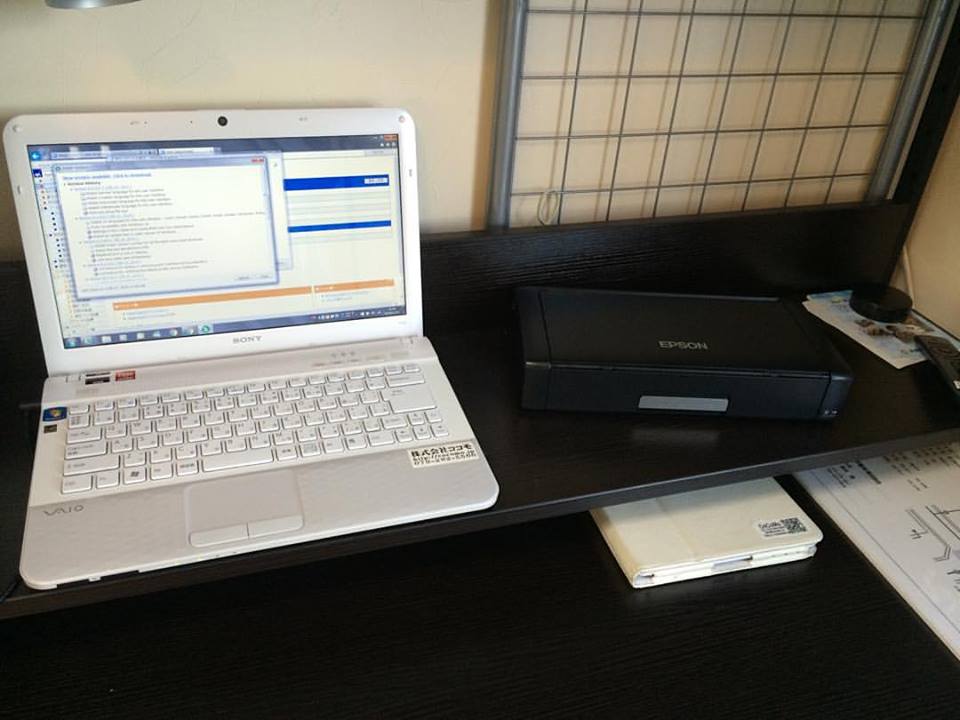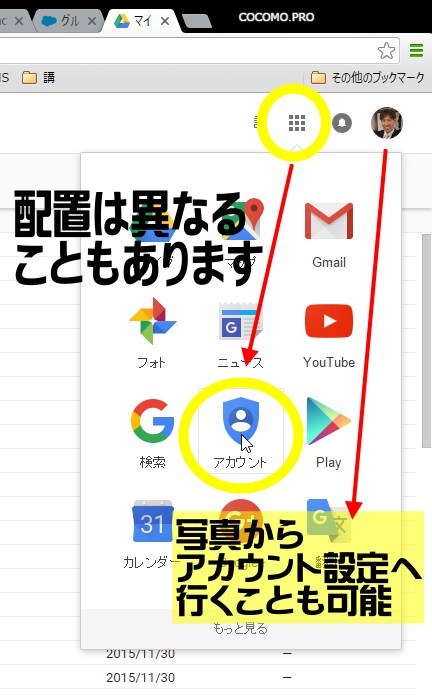今の生活から…定年後はどうなってるだろう?
今の生活から…定年後はどうなってるだろう?- その後は何年くらい生きるだろう?
- ライフスタイルはどうなってるだろう?
毎日の生活から将来へ目をやる”きっかけ”になる具体的な指標に「生存率」や「平均余命」がある。旅行でいう行程を決定していく前提の「期間の把握」にあたる。
プランニングやその必要性云々の前に、所用期間(?)を見てみよう。
-
概要
主な年齢の平均余命(H26)
-
これを読まれてるあなたの年代は?・・・
二十歳のころは時間が無限にあるように思えたが、40歳になるころには折り返しだと気づく。年々時間の流れる体感速度は、若いころに比べ加速していく。「時間の経つのが速いのは充実しているから・・・」とはいうものの、日々のやるべきことが増え、一方では制約が増えていくという変化のせいで「時間の感覚」が曖昧になっている。
長いようで短い飛行機の中では「到着までの残り時間」が気になり、ついついデスティネーションタイマーを確認してしまう。ここでは次の様な表で人生の到着までの時間を確認してみよう。人によって異なるが、平均的な数値を目にすると自分自身のプランニングに興味がわいてくるものだ。
- 20歳では あと60年もある。社会に出て何をしよう。
- 40歳では バリバリ働いてる。何度か健康診断にひっかかり、怪我もした。あと40年少々。
- 60歳では 今後、収入は年金と再就職として、体を壊した場合の25年程の対策はあるか。
- 80歳では 平均で言うと10年程は、ゆったり充実した時間を楽しめる体力と資金は大丈夫か。
-
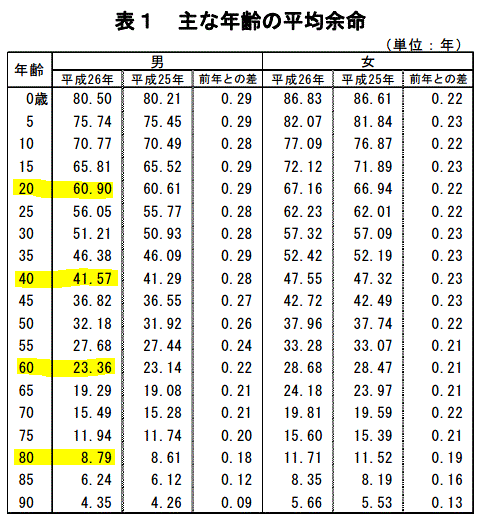
-
ある年齢までの生存可能性は?
-
現実的に生存率を考える(昭和60年生まれ)
(下記表3の中央部として)現在30歳で想像してみる。今、同世代の友達4人(自分を入れて5人)がいつまでみんなで集まれるか。
- 10年後:40歳ではまだほぼ全員会える可能性が高い
- 35年後:65歳になると一人は居ない可能性が高い
- 45年後:75歳では同様にほぼ二人居ないだろう
- 60年後:90歳では誰か一人だけ生存しているか誰も居ない
-
現実的な生存率を考える(昭和40年生まれ)
(同様に)現在50歳では:
- 現時点で5人中一人居なくてもおかしくない
- 15年後:65歳では二人が居ない可能性も…
- 25年後:75歳になると三人は居なくなっている
- 40年後:2.3%ということはほぼ誰も居ないだろう…
-
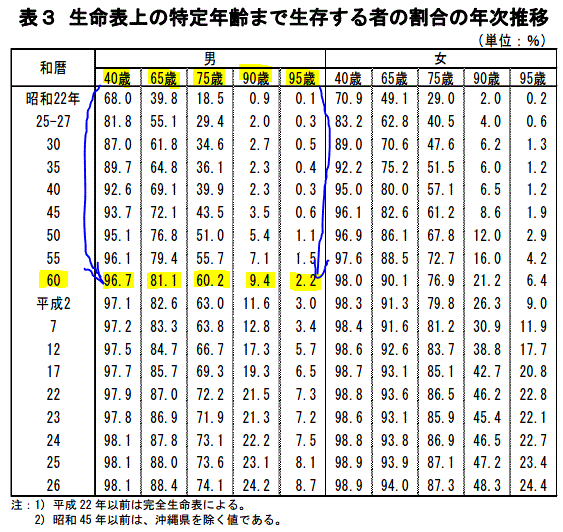
-
自分(家族)として考える
 家族で考えると、友達の例より更に身近な数字になり、様々な計画を立てるべき課題が見えてくる。夫婦、親、兄弟姉妹で、家族の将来についてプランニングしておく時間をとってみてはどうだろう。
家族で考えると、友達の例より更に身近な数字になり、様々な計画を立てるべき課題が見えてくる。夫婦、親、兄弟姉妹で、家族の将来についてプランニングしておく時間をとってみてはどうだろう。- 予定の収入が労働の場合、万一に備えた保障は?
- 保険は足りてるか。
- 余分な保険で資金を食ってないか。凍結させてないか。
- 増やせる保険は検討したか。
- 相続が発生した場合の配分と負担は?
- 誰が何を相続するかで法定相続分どおりにはならない場合は…。
- 急なことがあった時の意思を残す遺言は検討したか。
- 現預金の相続での相続税はそこから支払えばいいが不動産の場合はどうするか。
- 予定の収入が労働の場合、万一に備えた保障は?
-
「なかなか想像できない・・・」という人は
今後のプランニングに興味が出たら、旅先で”楽しい企画”を探しに旅情報が集まるツーリストへ立ち寄る気分で、FP(ファイナンシャル・プランンナー)オフィスなどへ寄り道してみてはどうだろう。何か良い行程表が見つかるかもしれない。
- 表:厚生労働省発表の「簡易生命表」など
- 本ページ